個人住民税の控除
控除とは
- 控除とは、所得金額から差引くことのできる金額で、扶養している家族の有無など個人の諸事情を住民税に反映させるためのものです。
- 住民税所得割額は、所得金額から控除金額を差引いて、残った所得(課税所得額)に税率を掛けて算出します。
- つまり、所得金額が同じであっても、控除金額が高い方が住民税額は低くなります。
- ただし、住民税均等割額については、控除金額を差引く前の所得金額が一定の金額を上回れば課税されますので、控除額は影響しません。
控除の種類
控除は、以下のように区分され、それぞれの要件を満たす場合は、定められた金額の合計額を所得金額から差引くことができます。
所得控除額の求め方
雑損控除
要件
前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合
控除額
下記のいずれか多い金額
- (損失額-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×10%)
- (災害関連支出の金額-保険等により補てんされた金額)-5万円
医療費控除
要件
前年中に医療費を支払った場合
控除額
(支払った医療費-保険等により補てんされた金額)-(総所得金額等×5%又は10万円のいずれか少ない金額)
控除限度額200万円
社会保険料控除
要件
前年中に社会保険料(国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料等)を支払った場合
控除額
支払った額
小規模企業共済等掛金控除
要件
前年中に小規模企業共済制度に基づく掛金又は確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金もしくは地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合
控除額
支払った額
生命保険料控除
要件
前年中に一般生命保険料、介護医療保険料又は個人年金保険料を支払った場合
控除額
一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険の区分ごとに計算した控除額の合計(介護医療保険は新契約のみ適用)
控除限度額70,000円
- 旧生命保険料控除…平成23年12月31日以前に契約締結した保険料を支払った場合(旧契約)
| 旧契約保険料支払額 | 控除額 |
|---|---|
| ~15,000円以下 | 支払った額 |
| 15,000円超~40,000円 | 支払った額×1/2+7,500円 |
| 40,000円超~70,000円 | 支払った額×1/4+17,500円 |
| 70,000円超~ | 35,000円(限度額) |
- 新生命保険料控除…平成24年1月1日以降に契約締結した保険料を支払った場合(新契約)
| 新契約保険料支払額 | 控除額 |
|---|---|
| ~12,000円以下 | 支払った額 |
| 12,000円超~32,000円 | 支払った額×1/2+6,000円 |
| 32,000円超~56,000円 | 支払った額×1/4+14,000円 |
| 56,000円超~ | 28,000円(限度額) |
- (注意)旧契約と新契約の両方の保険料を支払った場合
下記のいずれか多い金額- 旧契約で算出された控除額(控除限度額35,000円)
- 旧契約で算出された控除額+新契約で算出された
控除額 (控除限度額28,000円)
地震保険料控除
要件
前年中に地震保険料又は旧長期損害保険料を支払った場合
控除額
- 前年中に地震保険料だけを支払った場合
支払った地震保険料×1/2
控除限度額25,000円 - 前年中に旧長期損害保険料だけを支払った場合
| 旧長期損害保険料支払額 | 控除額 |
|---|---|
| ~5,000円以下 | 支払った額 |
| 5,000円超~15,000円以下 | 支払った額×1/2+2,500円 |
| 15,000円超~ | 10,000円(限度額) |
- (注意)前年中に地震保険料と旧長期損害保険料の両方を支払った場合
(1)及び(2)で算出された控除額の合計金額
控除限度額25,000円
障害者控除
要件
本人又は控除対象となる配偶者・扶養親族に障害がある場合
控除額
- 障害者控除 260,000円
身体障害者手帳3~6級
精神障害者保健福祉手帳 2級・3級
療育手帳 B1・B2等 - 特別障害者控除 300,000円
身体障害者手帳1~2級
精神障害者保健福祉手帳 1級
療育手帳 A1・A2等 - 同居特別障害者控除 530,000円
2.のうち同居を常況としている場合
※障害者手帳をお持ちでない方でも、要介護(支援)の認定を受けられている場合、障害者控除を適用できることがあります。詳細は下記ページ(ページID:1550)をご参照ください。
寡婦控除
要件
ひとり親に該当しない人で、次のいずれかに当てはまる人
- 夫と死別・離婚した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族等があり、前年の合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後再婚していない人や夫の生死が明らかでない人で、前年の合計所得金額が500万円以下の人
(注意)どちらも、住民票の続柄に「妻(夫)未届」の記載がある人は対象外
控除額
260,000円
ひとり親控除
要件
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じくする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者で、前年の合計所得金額が500万円以下の人
(注意)住民票の続柄に「妻(夫)未届」の記載がある人は対象外
控除額
300,000円
勤労学生控除
要件
本人の合計所得金額が75万円以下で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の勤労学生である場合
控除額
260,000円
配偶者控除
要件
- 配偶者控除…前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者かつ本人の合計所得金額が900万円以下の場合
控除額
330,000円
要件
- 老人配偶者控除…前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者で、70歳以上かつ本人の合計所得金額が900万円以下の場合
控除額
380,000円
配偶者特別控除
要件
前年の合計所得金額が48万円超133万円以下の生計を一にする配偶者(他の納税義務者の扶養親族、事業専従者を除く)を有し、かつ本人の合計所得金額が900万円以下の場合
控除額
| 配偶者の合計所得 (納税者本人の合計所得金額が900万以下) |
控除額 |
|---|---|
| 480,001~950,000円 | 33万円 |
| 950,001~1,000,000円 | 33万円 |
| 1,000,001~1,050,000円 | 31万円 |
| 1,050,001~1,100,000円 | 26万円 |
| 1,100,001~1,150,000円 | 21万円 |
| 1,150,001~1,200,000円 | 16万円 |
| 1,200,001~1,250,000円 | 11万円 |
| 1,250,001~1,300,000円 | 6万円 |
| 1,300,001~1,330,000円 | 3万円 |
| 1,330,001円以上 | 0円 |
扶養控除
要件
前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族がいる場合
控除額
- 年少扶養…16歳未満の扶養親族 0円
- 一般扶養控除…16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 330,000円
- 特定扶養控除…19歳以上23歳未満の扶養親族 450,000円
- 老人扶養控除…70歳以上の扶養親族 380,000円
- 同居老親…上記4.のうち、本人又は配偶者の直系尊属で同居の場合 450,000円
基礎控除
要件
合計所得金額が2,500万円以下の人
控除額
合計所得金額が、
- 2,400万円以下…430,000円
- 2,400万円超~2,450万円以下…290,000円
- 2,450万円超~2,500万円以下…150,000円
調整控除
個人町民税・県民税所得割額から次の算式で求めた金額が、調整控除として控除されます。
合計課税所得金額 (注1)が 200万円以下の場合
次の1.、2.のいずれか少ない金額×控除率(町3%・県2%)
- 所得税との人的控除額の差額の合計額(注釈2)
- 合計課税所得金額
合計課税所得金額が 200万円超の場合
{ 所得税との人的控除額の差額の合計額(注2)-(合計課税所得金額-200万円)} (注3)×控除率(町3%・県2%)
- (注釈1)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額をいいます。
- (注釈2)人的控除額の差は、下記の表のとおりです。((注意)納税者本人の所得金額が900万円以下の場合)
- (注釈3)この金額が5万円未満の場合は5万円とします。
- (注釈4)下記の表の配偶者特別控除欄の下段について控除額の差は5万円ですが、税制改正前(平成30年度まで)の控除額の差である3万円を適用します。(住民税33万円、所得税36万円)
| 人的控除の種類 | 住民税の控除額 | 所得税の控除額 | 控除額の差 |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 【障害者控除】普通障害者 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 【障害者控除】特別障害者 | 30万円 | 40万円 | 10万円 |
| 同居特別障害者 | 53万円 | 75万円 | 22万円 |
| 【寡婦・ひとり親控除】寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 【寡婦・ひとり親控除】ひとり親 | 30万円 | 35万円 | 5万円 |
| 勤労学生控除 | 26万円 | 27万円 | 1万円 |
| 【配偶者控除】一般配偶者 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 【配偶者控除】老人配偶者 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額48万円超50万円未満 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 【配偶者特別控除】配偶者の合計所得金額50万円以上55万円未満 | 33万円 | 38万円 | 3万円 |
| 【扶養控除】一般扶養 | 33万円 | 38万円 | 5万円 |
| 【扶養控除】特定扶養 | 45万円 | 63万円 | 18万円 |
| 【扶養控除】老人扶養 | 38万円 | 48万円 | 10万円 |
| 【扶養控除】同居老親等扶養 | 45万円 | 58万円 | 13万円 |
税額控除額の求め方
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。(ただし上場株式の配当において分離配当を選択した場合は、配当控除の適用はありません)
| 課税合計所得 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | 1,000万円超の部分 |
|---|---|---|---|---|
| 区分 | 町民税 | 県民税 | 町民税 | 県民税 |
| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |
| 【証券投資信託等】 外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |
| 【証券投資信託等】 外貨建等証券投資信託 |
0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合は、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
住宅借入金等 特別税額控除
所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった場合に、翌年度の個人町民税・県民税所得割額から差し引かれます。
居住開始年月日が、平成13年1月1日~平成18年12月31日又は平成21年1月1日~平成26年3月31日
次の1.又は2.のいずれか少ない方の金額となります。
- 前年分の所得税における住宅ローン控除可能額 - 前年分の所得税額(住宅ローン控除適用前)
- 前年分の所得税における課税総所得金額等×5%(97,500円を限度)
居住開始年月日が、平成26年4月1日~平成31年6月30日 特定取得(注釈1)以外
次の1.又は2.のいずれか少ない方の金額となります。
- 前年分の所得税における住宅ローン控除可能額 - 前年分の所得税額(住宅ローン控除適用前)
- 前年分の所得税における課税総所得金額等×5%(97,500円を限度)
居住開始年月日が、平成26年4月1日~平成31年6月30日 特定取得(注釈1)
次の1.又は2.のいずれか少ない方の金額となります。
- 前年分の所得税における住宅ローン控除可能額 - 前年分の所得税額(住宅ローン控除適用前)
- 前年分の所得税における課税総所得金額等 × 7%(136,500円を限度)
(注釈1)「特定取得」とは、居住者の住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、8%又は10%の消費税額等である場合における住宅の取得等をいいます。
寄附金税額控除
寄附金税額控除の対象は、都道府県・区市町村に対する寄附金、住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、都道府県・区市町村が条例で定める寄附金になります。
(注意)寄附金税額控除が適用される寄附金は、総所得金額等の30%が限度となります。
- 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(町民税6%・県民税4%
- 特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率×1.021)
(注意)特例控除額は、個人住民税所得割額の20%が限度です(平成27年度以前は、10%が限度)。
配当割額または株式等譲渡所得割額の控除
一定の上場株式等の配当等の所得に対しては、配当等の支払の際、所得税の源泉徴収とあわせて町・県民税が徴収されています。また、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡にかかる所得に対しても、所得税と町・県民税が徴収されています。これらの所得は、原則申告をしてもしなくてもよいことになっていますが、申告した場合は所得割の課税所得に含めて計算し、配当割額控除額または株式等譲渡所得割額控除額を税額控除後の町・県民税所得割額から控除します。
(1)配当割額控除額
町民税配当割額控除額=配当割額×5分の3
県民税配当割額控除額=配当割額×5分の2
(2)株式等譲渡所得割額控除額
町民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の3
県民税株式等譲渡所得割額控除額=株式等譲渡所得割額×5分の2
配当割額または株式等譲渡所得割額の還付及び充当について
配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額が町・県民税所得割額から控除することができなかった場合、納税義務者の当該年度分の町県民税均等割額に充当されます。充当することができなかった部分の金額については、還付(未納の町税がある場合にはその町税に充当)します。
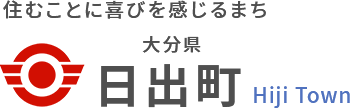







更新日:2025年11月21日