浄化槽のよくある質問
合併処理浄化槽について
基本的な使用方法は、普通の下水道を使うのと変わりはありませんので、これまでの Q&A を参照していただいて構いません。ただし、浄化槽は、微生物の力を借りて汚水を浄化しており、まさに「生き物」ともいえるものでありますので、使用に際しては、公共下水道などと異なり多少の注意が必要です。また、浄化槽は、設置申込みの際にご家族の人数など聞き取りさせていただいたように、使用者(使用人数など)にあわせて作られております。以下は、浄化槽を使用されている方に特にご注意いただきたいことでありますので、ご参考ください。
質問
合併処理浄化槽の補助金は新築の場合も対象となりますか?
回答
新築については補助金は出ません。以前は新築についても対象としていたのですが、現在は、既存の汲取り便槽もしくは単独処理浄化槽(トイレの汚水のみを処理する浄化槽)から合併処理浄化槽に設置替えを行なう場合のみ対象となっています。
質問
合併処理浄化槽の補助金を利用したいのですが手続きはどのようにしたらよいですか?
回答
まずは住民生活課 生活衛生係にお問い合わせください。補助対象となるかどうかや予算があるかどうかの確認を行います。(工事着工後の申請は受け付けられませんのでご注意ください)
問題なければ申請書類一式をお渡します。着工は交付決定通知書受領後となります。
(注意)申請書類は専門的な書類が多いので浄化槽の施工業者に代行手続きを依頼することをお勧めします。詳しくはパンフレットをご覧ください。
質問
浄化槽の保守管理はどうすればいいのでしょうか?
回答
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置ですから、微生物が活躍しやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切です。浄化槽の維持管理は、法定検査、保守点検、清掃に分かれますが、浄化槽法でそれぞれ定期的に実施することが義務づけられています。

浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月間、その後は1年に1回、大分県知事が指定した検査機関(財団法人大分県環境管理協会)の実施する法定検査を受けなければならないことが、浄化槽法で義務づけられています。
申し込み先
財団法人 大分県環境管理協会
〒870-1123 大分市大字寒田字下原409番地の40
電話番号 097-567-1855 ファックス 097-567-1926

浄化槽の保守点検は、機械の点検・補修や消毒剤の補給などを行います。浄化槽保守点検業者の登録制度が実施されていますので、登録業者に委託してください。保守点検を行う国家資格者として浄化槽管理士がいます。
お申込みは県知事登録業者へ
ご不明な場合は住民生活課 生活衛生係までお問い合わせください

浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取る作業を清掃といいますが、これは許可を受けた浄化槽清掃業者が行うことになっていますので、許可業者に委託してください。
お申込みは浄化槽清掃業者へ
ご不明な場合は住民生活課 生活衛生係までお問い合わせください
質問
ブロワーから音がしないのですが。
回答
ブロワーは、浄化槽内に空気を送り、槽内の微生物を活性化させ、汚水の浄化になくてはならない施設です。ブーンという音がしない場合は、ブロワーの電源が入っているかを確認し、それでも動かないようであれば、保守点検業者等にご連絡ください。
質問
旅行で2週間ほど家をあけるのですが、浄化槽の電源はどうしたら良いでしょうか
回答
この場合、浄化槽の電源というのは、ブロワーのことであると思います。電源は絶対に切らないでください。電源を切ると、このブロワーから空気が送られなくなり、浄化槽内の微生物が死んでしまい、浄化槽の働きが悪くなるばかりか臭気の原因となります。
質問
魚や野菜くずなどは、細かく砕いて流すと浄化槽内の微生物の餌(えさ)になると思うのですが。
回答
多少の野菜くずは、浄化槽の処理能力として引き受けられますが、微生物の餌としては、通常考えられる生活排水で十分です。台所から出る魚のアラ、野菜くず、食べ残しなどは、管を詰まらせる原因にもなりますので、できるだけ流さないよう排水口にネットをかぶせるなどご協力願います。
質問
風呂場のタイルに使うカビ取り洗剤を流しても大丈夫ですか?
回答
市販のカビ取り洗剤を大量に使うと、浄化槽内で働く微生物を殺してしまいます。適正量であれば問題はないかと思われますが、掃除の最後に浴槽の水を全て流すなど、多めの水で洗い流す処置をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
住民生活課 生活衛生係
〒879-1592 大分県速見郡日出町2974番地1
電話番号:0977-73-3128
ファックス:0977-72-7294メールフォームによるお問い合わせ
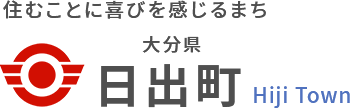







更新日:2022年11月29日