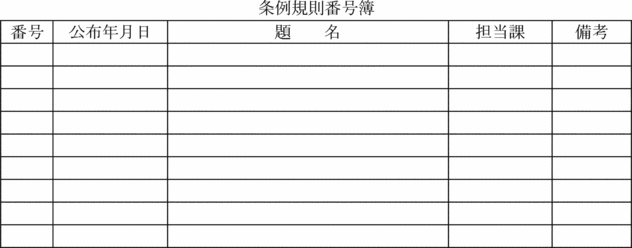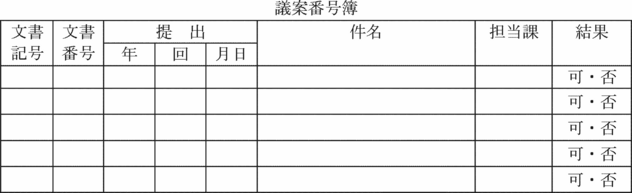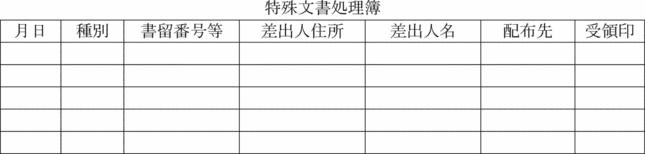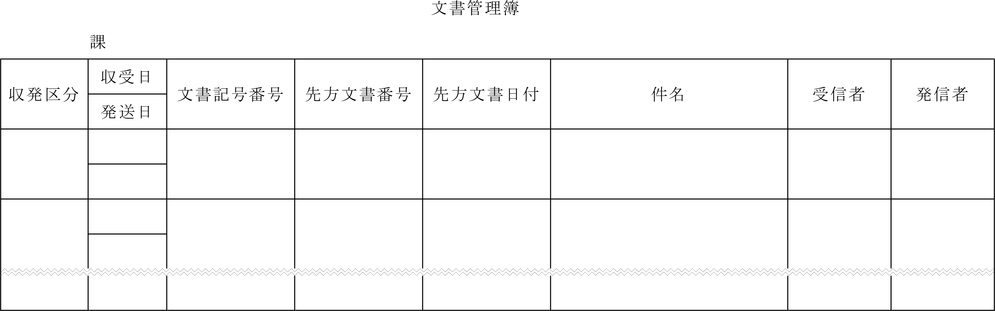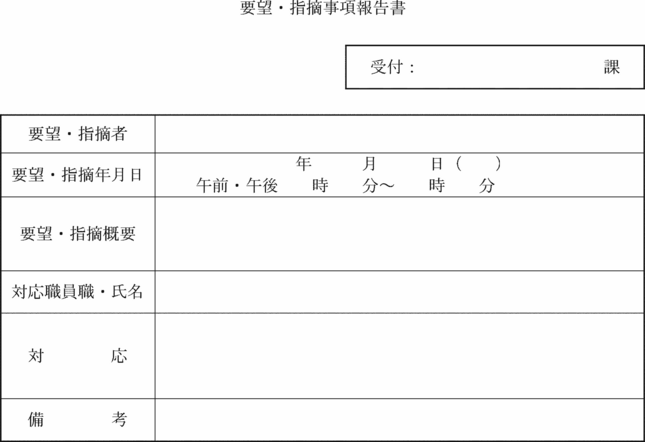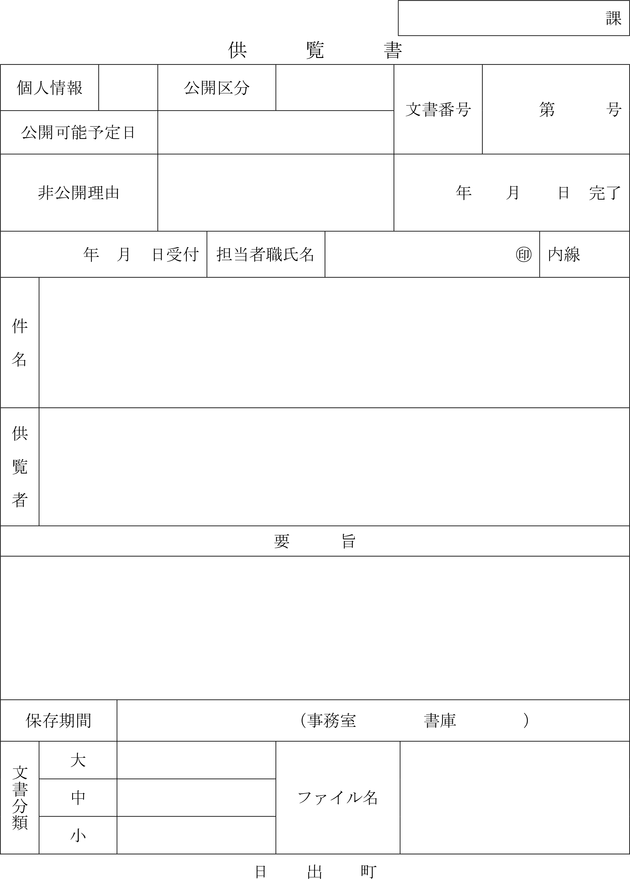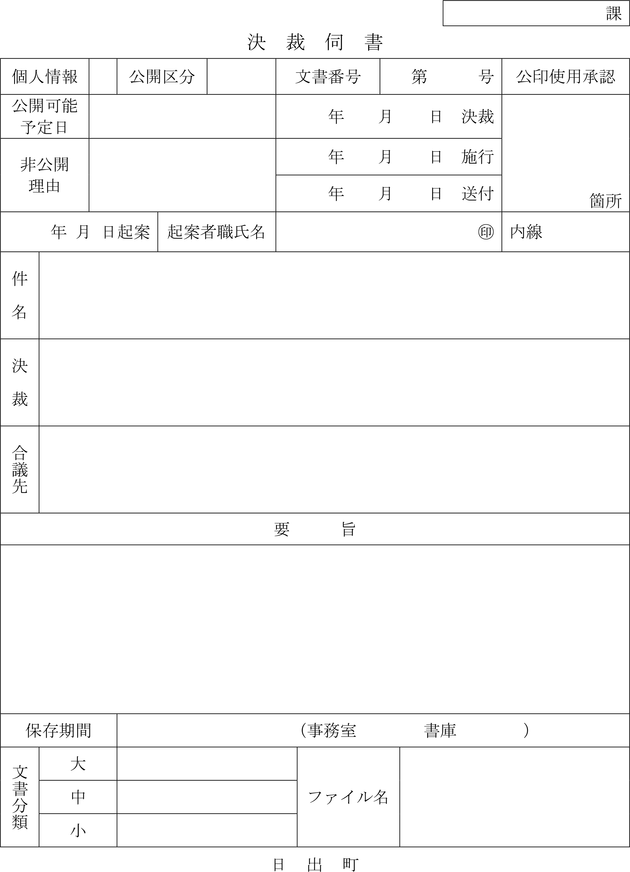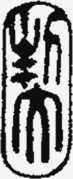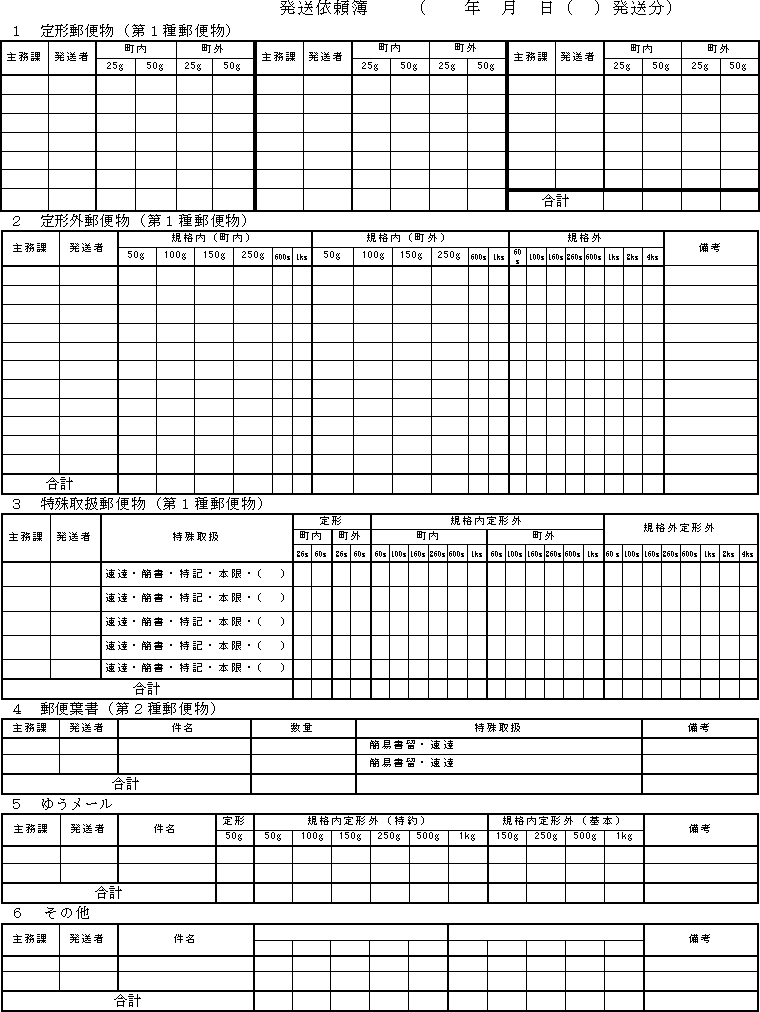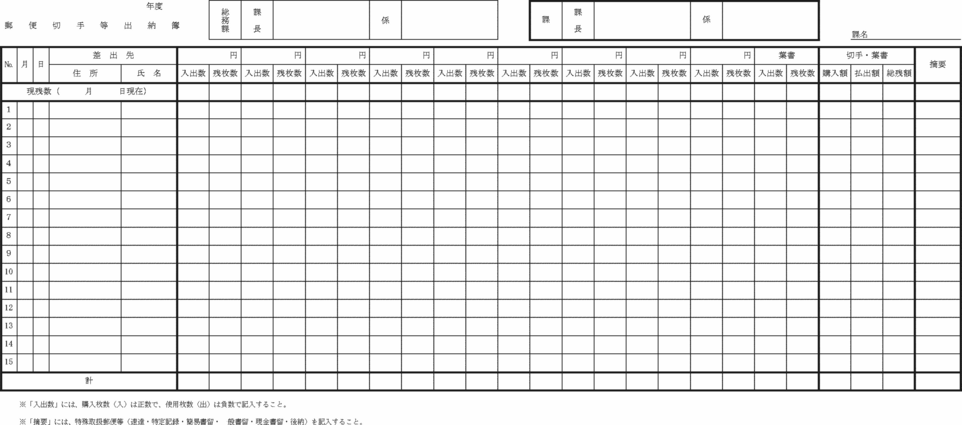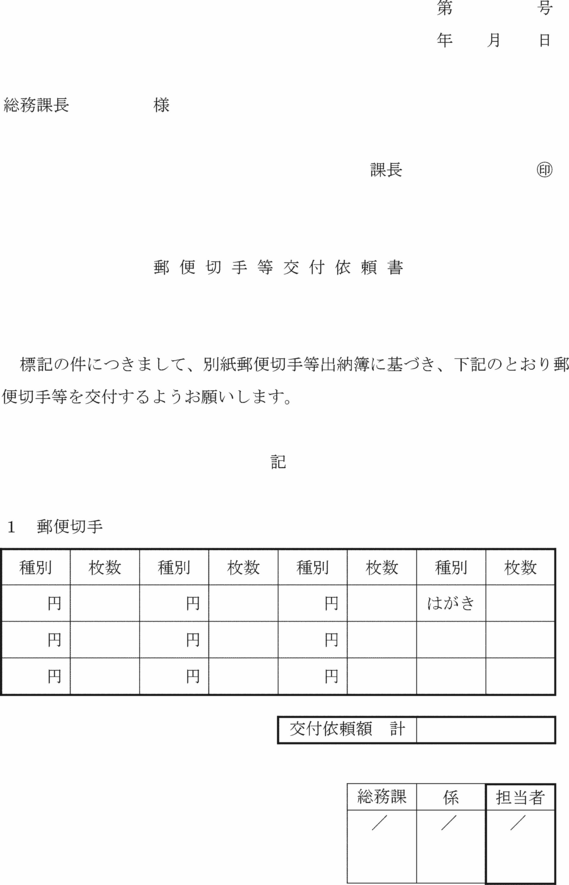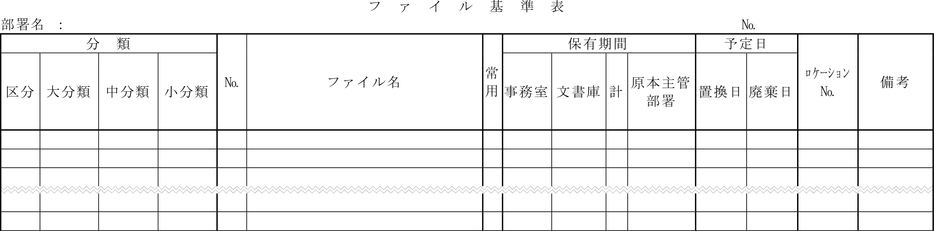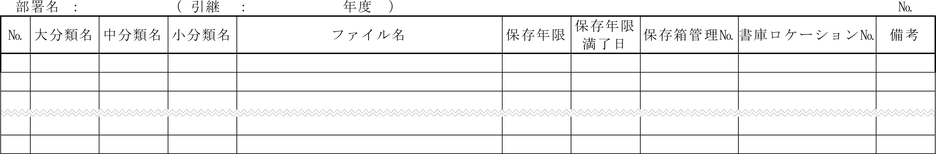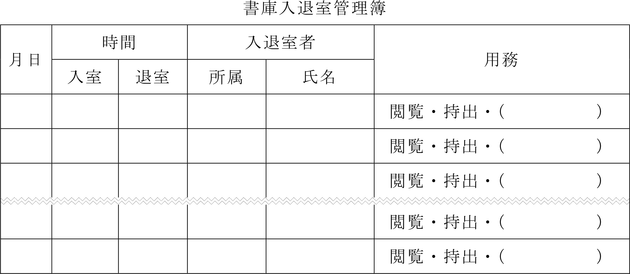○日出町文書管理規程
平成25年12月3日訓令第5号
日出町文書管理規程
日出町文書事務取扱規程(平成3年日出町訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 文書の種類(第8条―第12条)
第3章 文書の収受及び配布(第13条―第21条)
第4章 文書の処理(第22条―第32条)
第5章 文書の施行(第33条―第42条)
第6章 文書の保存(第43条―第55条)
第7章 雑則(第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、本町における事務の適性かつ能率的な運営を図るため、文書の管理に関し別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「文書」とは、職員が職務上作成し、又は取得した書類、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。
2 この規程において「電子文書」とは、文書のうち電磁的記録であって、書式情報(文書、表等を画面表示及び印字する際に指定する形式)を含めて文書管理システム、光ディスク等に記録されているものをいう。
3 この規程において「文書管理事務」とは、文書の作成、取得及び起案から保管及び廃棄に至るまでの文書の管理における全ての過程における事務をいう。
4 この規程において「文書管理システム」とは、文書の収受、供覧、起案、回議、決裁、保存、廃棄その他文書管理事務の処理を行うための電子情報処理組織で総務課が管理するものをいう。
8 この規程において「総合行政ネットワーク」とは、地方公共団体、国の間における情報交換の円滑化及び情報の共有による情報の高度利用を図るため、地方公共団体の組織内ネットワークを相互に接続した情報通信ネットワークをいう。
9 この規程において「決裁」とは、町長又はその補助機関の職員若しくは会計管理者がその権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
10 この規程において「起案」とは、決裁を得るための案を文書により作成することをいう。
11 この規程において「供覧」とは、収受した文書を関係する職員の閲覧に供することをいう。
12 この規程において「回議」とは、起案した文書(以下「起案文書」という。)について、起案者の直属上位の職員の承認を受けることをいう。
13 この規程において「合議」とは、起案文書に関連する他の課に属する職員の承認を受けることをいう。
(文書取扱いの原則)
第3条 事務及び事業に係る意思決定その他の事務処理については、文書を作成し、又は取得して処理しなければならない。ただし、事務処理に係る事案が軽微なものである場合は、文書の作成又は取得を省略することができる。
2 文書を作成し、又は取得した後における文書管理事務については、文書管理システムにより行うことを原則とする。
3 文書の取扱いは、正確、迅速、丁寧に行い、もって事務能率の向上に努めなければならない。
4
日出町情報公開条例(平成12年日出町条例第24号)第7条各号に規定する非公開情報、日出町個人情報保護条例(平成15年日出町条例第17号)第2条第1項に規定する個人情報並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号及び同条第8項に規定する特定個人情報(以下「個人情報等」という。)が記録されている文書並びに秘匿性を有する情報が記録されている文書(以下「秘密文書」という。)は、特に注意をして取り扱わなければならない。
(総務課長の責務)
第4条 総務課長は、本町における文書管理事務を統括し、各課における文書管理事務が適正かつ能率的に行われるように指導し、常にその改善に努めなければならない。
2 総務課長は、文書管理システムについて、十分な情報セキュリティ対策を講じ、かつ、常時適正に稼働するように維持管理しなければならない。
3 総務課長は、デジタル社会の発展に伴う情報通信技術の活用により、文書管理事務の簡素化及び効率化を図らなければならない。
(課長の責務)
第5条 課長は、その課における文書の内容について把握し、文書管理事務の処理が適性かつ能率的に行われるよう努めなければならない。
2 課長は、次に掲げる事務を行うとともに、その課に属する文書取扱主任及び文書取扱副主任並びに職員に対して指示及び指導を行う。
(1) その課における文書管理事務の処理状況の把握に関すること。
(2) その課における職員の文書管理意識の向上に関すること。
(3) その課における文書管理システムの稼働率の向上及び紙の文書の削減に関すること。
(文書取扱主任及び文書取扱副主任)
第6条 各課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、
組織規則別表第1に規定する各課の庶務を担当する係の長をもって充てる。
3 文書取扱主任は、課長を補佐し、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 文書管理事務の指導及び改善に関すること。
(2) 文書の収受、審査及び施行に関すること。
(3) 文書の処理促進に関すること。
(4) 文書の保管、廃棄及び引継ぎに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、文書管理事務及び文書管理システムに関すること。
4 文書取扱主任の事務を補助するため、文書取扱副主任を置く。
5 文書取扱副主任は、課長が指名する1人又は複数人をもって充てる。
6 各課長は、文書取扱副主任を指名したときは、総務課長に報告しなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、この規程その他の定めを遵守し、常に適正かつ能率的に文書管理事務を処理しなければならない。
2 職員は、文書管理システムを活用し、紙文書を削減するように努めなければならない。
3 職員は、文書を印刷するときは、情報の漏えいを未然に防ぐとともに用紙の節減を図るため、次に掲げるところにより、必要最低限の枚数とするよう努めなければならない。
(1) 文書の印刷は、真に必要な場合にのみ行うこと。
(2) 文書を印刷するときは、両面印刷等印刷機能の適切な設定を行うこと。
(3) 文書の複写は、前2号に準じて行うこと。
第2章 文書の種類
(文書の種類)
第8条 文書の種類は、次のとおりとする。
(1) 例規文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの
(2) 公示文書
ア 告示 法令等の規定又は職務上の権限に基づいて処分し、又は決定した事項を一般に公示するもの
イ 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するもの
(3) 令達文書
ア 訓令 職務執行上の基本的事項等について、所属の機関又は職員に対して指揮命令するもの
イ 指令 機関、団体、個人等に対し、申請、願い、伺い等に基づき、又は一方的に指示命令するもの
(4) 議案文書 議会に対して議決を求め、又は報告するもの
(5) 一般文書
ア 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの
イ 依頼 相手方に対し、一定の事項を頼むもの
ウ 照会 行政機関又は個人等に対し、特定の事項を問い合わせるもの
エ 回答 照会に対し、応答するもの
オ 諮問 附属機関その他一定の機関に対し、一定の事項について意見を求めるもの
カ 答申 諮問を受けた機関がその諮問を受けた事項について、意見を述べるもの
キ 報告 行政機関、委任者等に対し、一定の事項について、その事実、経過等を知らせるもの
ク 届け 一定の事項を行政機関等に知らせるもの
ケ 申請・願い 行政機関に対し、許可、認可、補助等一定の行為を求めるもの
コ 建議 附属機関等がその属する行政機関又は関係機関に対し、その調査審議した事項に関し将来の行為について、意見又は希望を申し出るもの
サ 勧告 行政機関が権限に基づき、住民又は指揮命令の関係のない機関に対し、一定の事項を申し出て、勧め、促すもの
シ 具申 国、県に意見や願望を申し出るもの
ス 内申 人事上の発令その他の機密上の処置を申し出るもの
セ 進達 経由すべきものとされている申請等を国、県等に取り次ぐもの
ソ 副申 進達する場合に参考意見を添えるもの
タ 協議 一定の行為をする場合に、その事項が他の行政機関の権限に関連するとき、相談するもの
チ その他 証明書、契約書、表彰文、儀式文、書簡文、請願文、陳情文、図画、電磁的記録であって他に該当しないもの
(文書の文書記号及び番号)
第9条 文書には、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める文書記号及び文書番号(以下「文書記号等」という。)を付さなければならない。
(1) 条例、規則、告示及び訓令 文書記号はその区分に従い「日出町条例」、「日出町規則」、「日出町告示」及び「日出町訓令」とし、文書番号は総務課においてその区分ごとに条例規則番号簿(
様式第1号)により暦年による一連の番号を付すること。
(2) 指令 文書記号は「指令」の文字の次に課ごとの文書記号一覧表(
別表第1)に定める文書記号を加えたものとし、文書番号は課ごとに文書管理システムにより会計年度による一連の番号を付すること。
(3) 議案文書 文書記号はその種類ごとに「議案」、「承認」、「同意」、「諮問」、「認定」、「報告」とし、文書番号は総務課においてその種類ごとに議案番号簿(
様式第2号)により暦年による一連の番号を付すること。
(4) 一般文書 文書記号は文書記号一覧表に定める文書記号とし、文書番号は第2号の規定の例により付すること。ただし、同一の件名又は同種の事案で多量に発生する文書については、文書管理システムで同一の文書番号の枝番号を付することができる。
2 文書番号は、文書管理システムにより、第14条第1項若しくは第20条第1項の収受の登録又は第22条第1項の規定により起案の登録をする際に付するものとする。
3 第1項第4号の規定にかかわらず、次に掲げる特に軽易な一般文書については、文書記号等を省略し、事務連絡で処理することができる。
(1) 単に事実を通知するもの
(2) 相手方に回答その他の一定の行為を求めないもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に軽易であると認められるもの
(文書の分類)
第10条 総務課長は、各課の事務及び事業の性質、内容等に応じ、系統的な文書の分類(以下「文書分類」という。)の基準を定めるものとする。
2 各課長は、前項の基準に従ってその課における文書分類を作成し、必要に応じて随時利用できるように文書を分類しなければならない。
3 各課長は、文書分類を作成したときは、総務課長に届け出なければならない。文書分類を変更したときも同様とする。
4 総務課長は、前項の規定により文書分類の届出を受けたときは、文書管理システムに登録しなければならない。
5 各課長は、文書管理システムにおける電子文書の文書分類を紙の文書と同一の文書分類により分類しなければならない。全庁で共有するファイルサーバについても同様とする。
(保存期間)
第11条 文書(次条に規定する常用文書を除く。)の保存期間は、1年未満の期間、1年、3年、5年、7年、10年、15年及び永年とし、文書保存期間の基準(
別表第2)の左欄の種別の区分に応じて、同表の中欄に定める期間を保存するものとし、同表の右欄の文書の種類を標準とする。
2 前項の規定にかかわらず、文書の保存期間について法令等に定めのある場合は、これに従う。
3 文書の保存期間は、保存期間が1年未満の期間であるものについては文書が完結した日の属する月の翌月から起算し、保存期間が1年以上の期間であるものについては文書が完結した日(事業が複数年にわたる文書については、その事業が終了した日)の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、歳入及び歳出に係る文書については、当該文書が属する会計年度の翌会計年度の6月1日から起算する。
4 前項の規定にかかわらず、例規文書、告示、訓令及び議案文書は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。
5 各課長は、保存期間を満了した文書の保存期間を必要に応じて1年単位で延長することができる。この場合においては、延長後の保存期間を文書管理システムに登録しなければならない。
6 各課長は、総務課長の承認を受けて、保存期間を満了していない文書の保存期間を短縮することができる。この場合においては、短縮後の保存期間を文書管理システムに登録しなければならない。
7 各課長は、保存期間を永年とする文書は、保存期間が30年を経過した際更に継続して保存する必要性を総務課長と協議の上決定するものとする。
(常用文書)
第12条 各課長は、前条第1項の規定にする基準に定めるもののほか、台帳、帳簿その他の常時使用する文書で各事務室内において保存期間を定めることが適当でないものを常用文書とすることができる。
第3章 文書の収受及び配布
(総務課における文書の収受及び配布)
第13条 到着した文書は、総務課において収受し、配布先の明らかな文書は封をしたまま、配布先の明らかでない文書は開封して配布先を確認し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める方法により配布しなければならない。
(1) 親展文書、書留文書、電報 当該文書の封筒の表面に文書収受印(
様式第3号)を押印し、特殊文書処理簿(
様式第4号)に必要事項を記載したうえ、直ちに文書取扱主任に配布し、受領印を受けること。
(2) 現金、金券及び有価証券 特殊文書処理簿に必要事項を記載し、文書取扱主任に配布し、受領印を受けること。
(3) 前号以外の文書 直ちに各課に配布すること。
2 前項の文書で収受の日時が権利の得喪又は変更に関係のあるものと認められるものは、当該文書に収受時刻を記載しておかなければならない。
3 2以上の課に関係のある文書は、総務課において、最も関係の深いと認める課に配布する。
4 配布先の明らかでない文書は、総務課長が当該文書の配布先の決定をし、当該主務課(当該文書に係る事務を所管する課をいう。以下同じ。)に配布するものとする。
(主務課における文書の取扱い)
第14条 文書取扱主任は、総務課から文書の配布を受けたときは、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定めるところにより配布し、事務担当者をして文書管理システムに収受の登録をし、文書に文書番号を記載しなければならない。ただし、ちらし、ポスターその他の特に軽易な文書であって収受した事実を記録する必要がないと認められるものは、文書管理システムへの登録を省略することができる。
(1) 親展文書 直ちに名宛人に配布すること。
(2) 親展文書以外の文書 総務課において既に開封されているものは直ちに、開封されていないものは開封した後、当該文書の余白に文書収受印を押印し、事務担当者に配布すること。
2 文書取扱主任は、前項の規定により総務課から配布を受けた文書が、その課の所管に属しないものであるときは、直ちに総務課に返付しなければならない。
3 親展文書の配布を受けた者は、当該文書が文書収受印を押印する必要があるものであるときは、当該文書の余白に文書収受印を押印しなければならない。
4 事務担当者の明らかでない文書は、現に配布を受けた課長が当該文書の事務担当者を決定し、事務担当者に配布するものとする。
5 事務担当者は、配布を受けた文書のうち重要なもの又は異例なものであるときは、処理方針の指示を受けるために上司の閲覧に供し、指示を受けなければならない。
6 主務課長は、文書管理システムにより文書管理簿(
様式第5号)を作成し、文書を収受したことを明らかにしなければならない。第22条第1項の規定による文書の起案についても同様とする。
(各課に直接到達した文書の取扱い)
第15条 各課に直接到達した文書は、課において前条各項の例により処理しなければならない。ファクシミリの設置課において文書をファクシミリにより受信した場合についても同様とする。
2 前項後段に規定する場合において、あらかじめファクシミリにより文書等を送信する旨の連絡を受けた受信者は、当該文書を受信予定時刻にファクシミリの設置課と連絡調整して受領させ、又はファクシミリの設置課において確実に受領しなければならない。
(閉庁日及び執務時間外に到着した文書の収受)
第16条 閉庁日及び執務時間外に到着した文書の収受は、当直員が収受し、総務課長に引き継ぐものとする。
(収受すべきでない文書)
第17条 到着した文書で収受すべきでないものについては、返送その他必要な処置をとらなければならない。
(郵便料金の不足又は未納の文書)
第18条 郵便料金の不足又は未納の文書は、官公署から発送されたもの又は総務課長が必要と認めたものに限り、その不足又は未納の料金を支払い、これを収受することができる。
(電話等による聴取)
第19条 各課において電話又は口頭で受理した事案のうち重要なものは、要望・指摘事項報告書(
様式第6号)に記載して取り扱わなければならない。
(電子文書の収受)
第20条 事務担当者は、文書管理システム、電子メール、総合行政ネットワーク、電子申請システム等により受信した電子文書及び電子記録媒体により到達した電子文書が、申請書、照会文書等当該文書に基づき指令、回答等を要するもの又はその他文書管理システムへの登録を必要と認めるものである場合は、文書管理システムにより収受の登録をし、文書に文書番号を記載しなければならない。
2 事務担当者は、電子メールにより到達した電子文書のうち、関係所属に対し照会、通知等を行う必要があるものについては、当該電子文書を電子メールにより転送することができる。この場合においては、照会文、通知文等の作成を省略することができる。
(収受文書の供覧)
第21条 事務担当者は、収受した紙の文書を供覧する必要がある場合は、文書管理システムにより作成した供覧書(
様式第7号)に当該文書を添付して供覧しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第14条第1項ただし書により文書管理システムへの登録を省略した文書を供覧する場合は、紙の文書の余白に供覧確認欄を設けて供覧することができる。この場合において、収受した文書が2以上の課に関係のあるときは、写しの配布その他適当な方法により、これを関係課に通知しなければならない。
3 事務担当者は、文書管理システムに収受の登録をした電子文書を供覧する必要がある場合は、電子供覧(文書管理システムを使用して電子文書を供覧することをいう。)をしなければならない。
第4章 文書の処理
(起案等)
第22条 文書の起案を行うときは、事務担当者(以下「起案者」という。)は、文書管理システムに登録することにより起案し、電子決裁処理(文書管理システムを使用して回議し、承認及び決裁を受けることをいう。以下同じ。)をしなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、電子決裁処理をすることが困難であると認められる場合は、起案者は、文書管理システムにより作成した決裁伺書(
様式第8号)に文書を添付することにより起案し、処理(以下「紙決裁処理」という。)をすることができる。
3 第1項の文書管理システムへの登録は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 件名は、非公開情報、個人情報等及び秘密情報を含まず、起案内容が分かる簡明なものとすること。
(2) 要旨は、起案の内容、経緯、処理方針、理由等について簡明なものとすること。
(3) 個人情報及び非公開情報の有無、非公開理由、保存期間、文書分類、ファイル名(第44条第3項に規定するファイル名をいう。)等を登録すること。
(4) 関係法規及び附属機関、庁議等の結果その他参考となる文書の電磁的記録を登録すること。
(5) 当該電子文書が秘密文書である場合は、パスワードの設定すること。
4 秘密文書の起案者は、当該文書に秘密文書である旨の表示をしなければならない。
5 起案文書について、紙決裁処理をする場合は、左とじとし、ホッチキス等で丁寧にとじること。ただし、右縦書きの文書の場合は、右とじとすることができる。
(文書の発信者名)
第23条 文書の発信者名は、法令に特別の定めのあるもののほか、町長の職氏名とする。ただし、事務連絡等の軽易と認められるものについては、課長の職氏名とすることができる。
2 各課に対する文書の宛先及び発信者名は、原則として課長の職氏名とする。
3 前2項の規定にかかわらず、照会に対する回答文書の発信者名は、照会文書の宛名を用いるものとする。
(決裁)
2 決裁権者又は専決権者は、不在となることが予定されているときは、あらかじめ電子決裁処理において代決する者を指定し、文書管理システムに登録しなければならない。
3 紙決裁処理において、起案文書の事案を代決した者は、その者の認め印の左上に「代」と記載しなければならない。この場合において、後閲を要するものについては、「後閲」と記載しなければならない。
(起案文書の持回り)
第25条 起案文書で事案が重要なもので説明を要するもの、特に緊急を要するもの又は秘密文書については、起案者又はその上席の職員が当該起案文書を自ら持ち回って決裁を受けなければならない。
2 前項の場合において、当該事案が電子決裁処理であるときは、文書管理システムに、説明を要する旨、特に緊急を要する旨又は秘密文書である旨の表示をしなければならない。
(合議)
第26条 起案の内容が他の課に関係のあるものは、主務課長の決裁を経た後、関係課長に合議しなければならない。
2 起案の内容が軽易であるものは、起案文書の写しの送付又は関係課と事前に協議することにより合議を省略することができる。
3 合議された事案に対して異議のあるときは、口頭をもって協議するものとする。この場合協議の整わないときは、主務課長は、その旨を付して上司の決裁を受けなければならない。
(総務課の審査)
第27条 次に掲げる事案に係る起案文書は主務課長の決裁を経た後、他の課に関係のあるものは当該関係課の合議を経て、総務課の審査を受けなければならない。
(1) 条例案、規則案、告示案、訓令案及び指令案
(2) 議案
(3) 法令及び例規の解釈に関する事案
(4) 私法上の法律関係の設定及び変更に関する事案で重要又は異例に属するもの
(5) 行政上及び民事上の争訟に関する事案
(6) 不服申立てに関する事案
(起案文書の修正、廃案等)
第28条 起案者は、回議及び合議を行っている起案文書の修正、廃案等を行う場合にあっては、起案文書を引き戻すことができる。
2 各職員は、起案文書に誤りがある場合その他回議及び合議を中断して起案者に修正等を促す必要がある場合は、起案者に起案文書を差し戻すことができる。
3 前2項の規定により引戻し、又は差戻しを受けた起案者が起案文書の修正を行った場合は、再度回議及び合議を行わなければならない。
4 職員は、下位の職員の不在等により起案文書の回議及び合議が行われない場合又は緊急の決裁を行う必要がある場合は、下位の職員よりも先に承認又は決裁を行うことができる。
5 起案者は、起案文書の決裁前において相当の理由がある場合は回議及び合議を行っている文書を、決裁後において決裁権者の指示を受けた場合は決裁が終了した文書を廃案にすることができる。
6 起案者は、起案文書が当初の趣旨と異なって決裁されたとき、又は廃案となったときは、その旨を回議及び合議を行った課長に通知しなければならない。
(緊急事案の処理)
第29条 緊急の処理を要する事案で正規の手続を経る暇のないものについては、口頭により決裁を受けて処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続による処理をしなければならない。
(決裁年月日の記載)
第30条 決裁済みの文書(以下「決裁文書」という。)には、その所定欄に決裁年月日を記載又は文書管理システムに登録をしなければならない。
(処理中文書の処理促進)
第31条 総務課長は、随時処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。
2 主務課長は、随時その課の主管に係る処理中の文書の処理状況を調査し、処理の促進を図らなければならない。
(処理中の紙の文書の整理)
第32条 主務課長は、処理中の紙の文書を全て一定の箇所に集め、適宜分類整理し、その所在を明らかにしておかなければならない。
第5章 文書の施行
(浄書及び校合)
第33条 決裁文書の浄書は、主務課において行う。ただし、表彰状その他総務課長が適当と認める文書は、総務課において行う。
2 決裁文書の浄書は、正確及び明瞭に行わなければならない。
3 決裁文書で浄書した文書(以下「浄書文書」という。)の日付は、浄書文書を施行する日とする。
4 事務担当者は、必ず浄書文書と決裁文書を校合しなければならない。
(文書の審査)
第34条 浄書文書のうち、重要なもの、慎重を期すべきものその他審査を受ける必要があるものについては、文書取扱主任の審査を受けるものとする。
(公印の押印)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる軽易な一般文書は、公印の押印を省略することができる。この場合においては、当該文書の左上に「公印省略」の表示をしなければならない。
(1) 住民の権利又は義務に影響しないもの
(2) 国又は地方公共団体間の照会又は回答に関するものであって、軽易な事項に関するもの
(3) 町の機関の内部又は町の他の機関に対して施行するもの
3 総合行政ネットワーク又は電子申請システムにより施行する電子文書には、
日出町電子署名規程(平20年日出町訓令第2号)の定めるところにより、電子署名を行うものとする。ただし、前項各号に掲げる軽易な一般文書である電子文書電子文書であるときは、これを省略することができる。
(主務課における発送文書の処理)
第36条 発送を要する文書は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める処理をして、原則として総務課長に送付するものとする。
(1) 発送する文書 必要な包装をし、主務課名及び係名を記載の上、文書取扱主任において取りまとめ、午後3時30分までに総務課長に送付すること。
(2) 電報又は電子郵便による文書 総務課長が指示する方法により発送すること。
2 文書取扱主任は、前項の規定より文書を総務課長に送付する場合は、その指示に従い、次の各号に掲げる区分により、当該各号に定める処理をしなければならない。この場合において、書留、特定記録等で発送するものにあっては、書留・特定記録郵便物等差出票を作成しなければならない。
(1) 料金計器別納の取扱いとする場合 郵便料金計器(郵便法(昭和22年法律第165号)第85条第1項に規定する郵便料金計器をいう。以下同じ。)を使用し、郵便物に料金を表す印影を表示すること。
(2) 料金後納の取扱いとする場合 総務課長の指示するところによる仕分をし、発送依頼簿(
様式第10号)に記載すること。
(3) 前2号に掲げる取扱い以外の取扱いとする場合 総務課長の指示するところによること。
3 総務課長は、前項の指示をするときは、効率的に処理し、かつ、最も経費を抑制できる方法によらなければならない。
4 事務担当者等が直接文書を持参し施行する場合は、文書の紛失、盗難等に注意し、確実に手渡さなければならない。
5 文書取扱主任は、文書を施行するときは、事務担当者をして施行年月日及び送付年月日を決裁文書の所定欄への記載又は文書管理システムへの登録をしなければならない。
(総務課長による発送)
第37条 総務課長は、前条の規定により文書の送付を受けたときは、その日分を取りまとめ、料金後納郵便物差出票その他の必要な書類を添えて郵便局その他の事業者に差し出さなければならない。この場合において、書留又は特定記録にするものは、更に書留・特定記録郵便物等差出票を添付しなければならない。
(電子文書の施行)
第38条 電子文書は、文書管理システム、電子メール、総合行政ネットワーク、電子申請システム又は電子掲示板(庁内ネットワークにおいて職員が用いるものに限る。以下同じ。)により主務課において施行することができる。
2 文書管理システム、電子メール又は電子掲示板により施行することができる電子文書は、第35条第3項ただし書に規定する軽易な一般文書である電子文書に限るものとする。
3 町の機関又は特定の課に対して施行する電子文書は、文書管理システムにより施行することを原則とする。
4 町の機関又は課に対して施行する電子文書であって、周知を目的としたもの及び施行先の町の機関又は課において収受、供覧等をする必要がないと認められるものにあっては、電子掲示板により施行することができる。
(ファクシミリによる施行)
第39条 ファクシミリによる施行ができる場合は、施行先の相手が電子メールを使用できる機器を有さない場合その他前条第1項の規定による施行ができない場合であって郵送若しくは持参による暇がない場合又は施行先の相手が求める場合に限るものとする。
2 文書をファクシミリで施行するときは、主務課において行うものとし、施行後当該決裁文書に施行年月日を記載又は文書管理システムに登録をしなければならない。
3 ファクシミリで施行することができる文書は、第35条第2項各号に掲げる軽易な一般文書であって、かつ、公印を押印しない文書とする。ただし、個人情報等が記録されている文書、秘密文書その他文書の形式又は内容から判断してファクシミリによる送信に適さない文書は、この限りでない。
4 ファクシミリにより前項の文書を送信しようとするときは、次に定めるところによるものとする。
(1) 送信者は、文書の内容に応じて、あらかじめ受信者に対してファクシミリにより送信する旨及び送信予定時刻を連絡すること。
(2) ファクシミリによる施行は、決裁文書をファクシミリの設置課の文書取扱主任に提示してその承認を受け、自らファクシミリを操作して送信すること。
(3) ファクシミリによる施行は、全ての送信原稿の余白に枚数及びページを記載し、受信者氏名又は宛先及び送信者の所属、職氏名、連絡先等を記載した文書を添えること。
(閉庁日及び執務時間外における文書の施行)
第40条 閉庁日及び執務時間外(午後3時30分以降を含む。)において文書を施行するときは、あらかじめ執務時間内に総務課長から郵便切手の交付を受け、主務課において発送するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行する文書が多量である場合は、総務課長が指示する方法により発送することができる。
(郵便切手等の管理)
第41条 主務課長は、主務課において発送する文書に使用する郵便切手及び郵便葉書についてその金額を郵便切手等出納簿(
様式第11号)に差出先、金額等の出納を記載して、適正に管理しなければならない。
2 主務課長は、郵便切手等出納簿に基づき、郵便切手等交付依頼書(
様式第12号)により、総務課長に対して郵便切手及び郵便葉書の交付を依頼することができる。
3 総務課長は、当日の郵便料金計器の使用状況を記録し、郵便料金計器による料金を表す印影で使用しなかったものを適正に処理しなければならない。
(文書の完結)
第42条 文書の完結の日は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。
(1) 条例、規則、訓令及び告示 公布又は公示された日
(2) 契約関係文書 当該契約事項の履行が完了した日
(3) 歳入及び歳出に係る文書 当該出納のあった日
(4) 訴訟関係書類 当該事件の完結した日
(5) その他一般文書 当該文書の事案が施行された日
第6章 文書の保存
(主務課における保管)
第43条 事案の処理が完結した文書で保存期間の満了しないもの(電子文書を除く。以下「完結文書」という。)は、原則として当該事案の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の終了の日までの間(以下「保管期間」という。)、主務課長が保管するものとする。
2 主務課長は、完結文書を次条の規定により作成したファイルに挟み、第45条の規定により作成したファイルボックスに収納して、主務課の事務室内の共用の棚等に整理し、整頓して保管なければならない。
3 前項の規定にかかわらず、常用文書は、主務課長が保管しなければならない。
4 個人番号を記録した文書は、施錠できる棚等に保管しなければならない。
5 前3項の規定は、事案の処理が完結していない文書について準用する。
(ファイルの作成)
第44条 事務担当者は、総務課長の定めるところにより、文書取扱主任の指示を受けて、ファイルを作成しなければならない。
2 ファイルは、総務課長の指定するフォルダを用いることとし、完結文書を次に掲げる基準により区分したものごとに作成しなければならない。
(1) 完結文書の事案又は内容ごとに作成すること。
(2) 会計年度、月、日等文書の作成された期日ごと及び保存期間ごとに作成すること。
(3) 完結文書の施行先ごとに作成すること。
(4) 第8条の文書の種類ごとに作成すること。
(5) 事案の発生から完結までの段階ごとに作成すること。
(6) 1個のファイルは、紙の枚数がおおむね50枚から80枚までを限度として作成すること。
3 フォルダには、ファイルの名称(以下「ファイル名」という。)、主務課、保存期間、文書分類等を表示したラベルを文書管理システムにより作成し、これを貼付しなければならない。
4 ファイル名の基準は、次のとおりとする。
(1) 事務担当者以外の者でも分かりやすいファイル名とすること。
(2) 抽象的な名称を用いず、簡潔かつ具体的なファイル名とすること。
(3) 他と区別できるファイル名とすること。
(4) ファイル名は、文書を作成し、又は取得した日の属する年度を含めること。
5 電子文書のファイルは、文書管理システムにおいて紙の文書と同一のファイル名(紙の文書が存在しない場合にあっては、前項の基準によるファイル名)としなければならない。
(ファイルボックスの作成)
第45条 事務担当者は、総務課長の定めるところにより、文書取扱主任の指示を受けて、ファイルボックスを作成しなければならない。
2 ファイルボックスには、文書分類、ファイル名、主務課名等を表示したラベルを文書管理システムにより作成し、これを貼付しなければならない。
3 ファイルボックスには、前項の規定により表示されたファイル名以外のファイルを収納してはならない。
(文書の保管の特例)
第46条 前2条の規定にかかわらず、形状等によりフォルダ及びファイルボックスによる保管が困難な完結文書については、適宜簿冊、箱等により保管することができる。この場合においては、第44条第3項及び第4項の規定の規定を準用する。
(ファイル基準表)
第47条 主務課長は、新たに保管することとなったファイルについて、文書管理システムによりファイル基準表(
様式第13号)を作成しなければならない。
2 ファイル基準表には、文書分類表に基づく分類、ファイル名、保存期間等を記載しなければならない。
(文書の引継ぎ)
第48条 総務課長は、第43条第1項の保管期間を満了した文書(保存期間が1年未満及び1年のものを除く。次項において同じ。)について、主務課長に対し、引継ぎの確認を求めなければならない。
2 前項の照会を受けた主務課長は、引継ぎを行う文書について、文書取扱主任をして文書保存箱を作成し、速やかに総務課長に書庫への移管を届け出なければならない。
3 主務課長は、文書保存箱に収納したファイルを文書管理システムに登録しなければならない。
4 主務課長は、総務課長と協議の上、必要があると認める場合は、保管期間を満了した文書の保管期間を1年単位で延長し、自ら保管することができる。
(総務課長による保管)
第49条 総務課長は、前条第1項に規定により届けられた完結文書の移管を適当と認めるときは、書庫における文書保存箱の配架場所を指定しなければならない。
2 前項の指定を受けた課長は、作成した文書保存箱を指定された書庫における場所に配架し、文書管理システムに登録しなければならない。
3 文書保存箱には、文書管理システムにより作成した文書保存リスト(
様式第14号)を同梱し、配架場所等を表示したラベルを貼付しなければならない。
4 総務課長は、書庫に移送された完結文書を当該完結文書の保存期間が満了する日まで書庫に収蔵し、適切に整理し、保管しなければならない。
(書庫に収蔵した完結文書の閲覧等)
第50条 職員は、総務課長が保管する書庫に収蔵した完結文書を閲覧し、又は持ち出すときは、文書管理システムにより貸出申請をしなければならない。
2 前項の規定により閲覧又は持出しをする完結文書は、他に転貸し、又は抜取り、取替え、訂正等をしてはならない。ただし、日出町個人情報保護条例第23条の2の規定による個人情報の訂正をする場合は、この限りでない。
(書庫の管理)
第51条 総務課長は、書庫の管理に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 常に清掃し、整理しておくこと。
(2) 火災、水害その他の災害及び盗難の予防に努めること。
(3) 湿気、虫害等の予防に努めること。
(4) 施錠等の措置を講じ、入退室を管理すること。
2 書庫に入退室するときは、書庫入退室管理簿(
様式第15号)に記入した上で入退室しなければならない。この場合において、入退室する者が職員以外のものであるときは、その用務に関連する職員が立ち会わなければならない。
3 総務課長は、文書が被災した場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
4 町長は、文書の被災状況に応じて、大分県立公文書館又は独立行政法人国立公文書館に、文書の修復に関し必要な支援を求めるものとする。
(文書の所管換え)
第52条 組織改正、事務分掌の変更等により、文書の所管に変更があったときは、当該文書を現に保管している主務課長は、所管換えを行わなければならない。
2 所管換えをする文書を保管している主務課長は、所管換えをする文書のファイル基準表及び文書保存リストに基づき、当該文書の所管換えについて、新たに当該文書の所管をすることとなる主務課長に協議をしなければならない。
3 前項の協議が整ったときは、現に文書を保管している主務課長は、当該文書にファイル基準表及び文書保存リストを添えて、速やかに、当該文書の引渡しを行わなければならない。
4 文書の新たな主務課長は、引渡しを受けた文書並びにファイル基準表及び文書保存リストを確認し、総務課長に報告しなければならない。
5 総務課長は、所管換えをされた文書について、文書管理システムに登録された事項を変更しなければならない。
(保存期間を満了した文書の取扱い)
第53条 総務課長は、その保管する文書で保存期間の満了したものについて、主務課長に廃棄の可否を照会しなければならない。
2 主務課長は、前項の照会に対し、第11条第4項の規定による保存期間の延長の必要性を検討し、廃棄の可否を回答しなければならない。この場合において、主務課長は廃棄を可能とする文書について廃棄の承認をしなければならない。
3 主務課長は、保存期間が1年未満及び1年の文書その他書庫への移管をしない文書が保存期間を満了した場合は、廃棄の承認を行った上で、総務課長に届け出なければならない。
4 主務課長は、保存期間の満了した文書であっても、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める機関が経過するまでの間、廃棄してはならない。
(1) 現に監査、検査等の対象となっているもの 当該監査、検査が終了するまでの間
(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間
(3) 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決の日の翌日から起算して1年間
(5) 日出町個人情報保護条例第13条第1項又は第2項に規定する開示請求があったもの 日出町個人情報保護条例第18条第1項又は第2項の規定による決定があった日の翌日から起算して1年間
5 総務課長は、第2項及び第3項の規定により、主務課長が廃棄の承認をした文書であっても行政活動の記録として保存すべきものが含まれている場合は、主務課長に当該文書の保存期間を延長させなければならない。
(文書の廃棄)
第54条 総務課長は、毎年1回前条第2項の規定により廃棄の承認を行った文書を廃棄しなければならない。
2 主務課長は、前条第3項の規定により廃棄の承認をした保存期間が1年未満及び1年の文書を廃棄しなければならない。
3 主務課長は、文書管理システムに記録された電子文書について、関連する紙の文書が存在する場合にあっては第1項の規定により紙の文書を廃棄した後に、紙の文書が存在しない場合にあっては前条第2項の承認をした後に、総務課長に対し、当該電子文書の廃棄の処理を依頼しなければならない。
4 総務課長は、前条第2項及び第4項の規定により保存期間の延長の申出があった場合並びに同条第5項の規定により保存期間を延長させた場合は、期間を定めて保管することができる。
(廃棄文書の処理)
第55条 前条第1項の規定により文書を廃棄する場合に当該廃棄文書中に印影等移用のおそれのあるもの又は秘密文書は、裁断、焼却等の適当な措置を講じなければならない。
2 個人番号を記録した文書又は電子文書については、保存期間を経過した場合、できる限り速やかに個人番号を消去し、光ディスク等を裁断、破砕等の復元できない手段で削除又は廃棄しなければならない。
3 総務課長は、前条第3項の規定により電子文書の廃棄の処理の依頼を受けた場合は、町長の承認を受けて、文書管理システムから電子文書を消去するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第56条 この規程に定めるもののほか、文書の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第8条、第9条第1号及び第3号、第10条並びに第42条第1号は、平成26年1月1日から施行する。
(日出町事務決裁規程の一部改正)
(次のよう略)
附 則(平成27年10月2日訓令第15号)
この訓令は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年3月7日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月29日訓令第7号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月14日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月17日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和2年6月23日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附 則(令和4年4月28日訓令第8号)
この訓令は、令和4年5月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
文書記号一覧表
課名 | 文書記号 |
総務課 | 日総 |
財政課 | 日財 |
政策企画課 | 日政企 |
まちづくり推進課 | 日ま推 |
税務課 | 日税 |
住民生活課 | 日住生 |
介護福祉課 | 日介福 |
子育て支援課 | 日子 |
健康増進課 | 日健 |
農林水産課 | 日農 |
都市建設課 | 日都 |
会計課 | 日会 |
別表第2(第11条関係)
文書保存期間の基準
種別 | 保存期間 | 文書の標準 |
第1種 | 永年 | 1 議決書その他議会に関する重要なもの |
| | 2 条例、規則、告示、訓令及びその基礎となるもの |
| | 3 町政の沿革に関する重要なもの |
| | 4 任免、賞罰、身分等の人事に関する重要なもの |
| | 5 退職年金及び遺族年金等に関するもの |
| | 6 儀式及び表彰に関する重要なもの |
| | 7 訴訟及び不服申立てに関する重要なもの |
| | 8 調査、統計、報告、証明等に関する特に重要なもの |
| | 9 事務引継に関する重要なもの |
| | 10 財産に関する重要なもの |
| | 11 町債及び借入金に関する重要なもの |
| | 12 保存文書に関する重要なもの |
| | 13 認可、許可、承認等の行政処分に関する特に重要なもの |
| | 14 契約に関する特に重要なもの |
| | 15 市町村の設置、分合、境界変更及び名称の変更に関する文書 |
| | 16 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの |
| | 17 総合計画、都市計画その他の計画に関する特に重要なもの |
| | 18 原簿、台帳等で重要なもの |
| | 19 その他永年保存の必要を認められるもの |
第2種 | 15年保存 | 法令の規定により15年間の保存が定められているもの |
第3種 | 10年保存 | 1 国又は県の訓令、指令、通知その他重要なもの |
| | 2 認可、許可、承認等の行政処分に関する重要なもの |
| | 3 契約、覚書、協定その他権利義務に関する重要なもの |
| | 4 原簿及び台帳 |
| | 5 寄附受納に関する重要なもの |
| | 6 予算、決算及び出納に関する帳票及び証拠書類 |
| | 7 物品の出納簿 |
| | 8 租税その他各種公課に関するもの |
| | 9 議会に関するもの |
| | 10 陳情、請願、要望に関するもの |
| | 11 調査、統計、報告、証明等に関する重要なもの |
| | 12 補助金等に関する重要なもの |
| | 13 災害救助に関するもの |
| | 14 附属機関に関するもの |
| | 15 職員の給与に関するもの |
| | 16 その他10年保存の必要を認められるもの |
第4種 | 7年保存 | 法令の規定により7年間の保存が定められているもの |
第5種 | 5年保存 | 1 補助金等に関する書類 |
| | 2 予算、決算及び出納に関するもの |
| | 3 調査、統計、報告、証明等に関するもの |
| | 4 工事又は物品に関するもの |
| | 5 認可、許可、承認等の行政処分に関するもの |
| | 6 契約、覚書、協定その他権利義務に関するもの |
| | 7 その他5年保存の必要を認められるもの |
第6種 | 3年保存 | 1 一般行政事務の施策に関するもの |
| | 2 会計経理に関する一般文書 |
| | 3 当直日誌、出勤簿、旅行命令簿等職員の勤務の実態を証するもの |
| | 4 照会、回答その他往復文書に関するもの |
| | 5 文書の受付及び発送に関するもの |
| | 6 その他3年保存の必要を認められるもの |
第7種 | 1年保存 | 1 軽易な照会、回答、願い、届け等 |
| | 2 前各項及び次項に掲げる以外のもの |
第8種 | 1年未満の期間保存 | 1 別途、正本・原本が管理されている文書の写し |
| 2 ちらし、ポスターその他これらに類するもので町が収受したもの |
様式第1号(第9条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第13条関係)
様式第4号(第13条関係)
様式第5号(第14条関係)
様式第6号(第19条関係)
様式第7号(第21条関係)
様式第8号(第22条関係)
様式第9号(第35条関係)
様式第10号(第36条関係)
様式第11号(第41条関係)
様式第12号(第41条関係)
様式第13号(第47条関係)
様式第14号(第48条関係)
様式第15号(第51条関係)